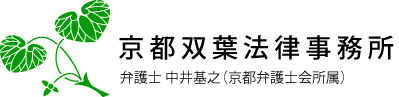5.
似たデザインも出願しておくと有利です。
・「似てる!」がポイントです。
テレビ番組で、中国のドラえもんの偽物を観たことがある人も多いと思います。その偽物のドラえもんでも、全く同じデザインではなく、「似てる!」というレベルです。意匠権侵害の場合も、全く同じのものはほとんどなく、似ているものがほとんどです。法律では、この「似ている」を「類似」と呼んでおりますが、この「類似の範囲」がまた曖昧なのです。一応の基準はあるのですが、判断する人によって異なるのは事実です。
一つの意匠登録出願では一つのデザインしか指定できません。そうすると、そのデザインを中心として「類似の範囲」が決まります。それなら、その中心に類似するデザインの意匠権を複数持てば、それぞれの意匠権にもそれぞれの類似の範囲があるので、意匠権の範囲が必然的に広がるのです。つまり、似たデザインをいくつか出願しておけば効果的なのです。それを「関連意匠」といいます。
・関連意匠とは
関連意匠の出願をする時は、いくつかのデザインの中で「中心」となるものを選びます。他のものが、その「中心」となるものに全て似ていることが条件です。似ているもの(中心以外のもの)同士が似ている必要はありません。
例えば、いくつかのデザイン(A、B、C)を考えたとします。AはBとCに類似しますが(似ていますが)、BとCは類似していても、類似していなくてもどちらでも構いません。その場合は、Aが「中心」になります。その中心のものを「本意匠」といいます。他のものを「関連意匠」といいます。BやCを本意匠にすると少しややこしいことになりますので、注意が必要です。
・関連意匠の意匠権について
関連意匠の意匠権もそれぞれ独自の権利になります。AとBとCの意匠権のうち、Cだけに類似する(似ている)製品が出回った時は、Cの意匠権に基づいて意匠権侵害だと言えますし。BにもCにも似ているのなら、両方の意匠権の侵害だと言うこともできます。
・デメリットもあります。
それぞれ出願しなくてはならず、意匠権もそれぞれなので、3つあれば、3倍の料金になってしまいます。
代理人の手数料が安くなる場合がありますので(図面によりますが)、交渉してみて下さい。国の手数料は安くなりません。
一度、登録になれば(意匠権が発生すれば)、意匠公報というものにそのデザインが公開されます。公開されると、そのデザインはもう二度と別の人が登録できなくなるので、他人に取られることがないメリットがあります。そのメリットのために、1年間分の登録料だけ支払うのも手です。