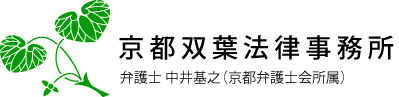2.
特許出願しないと特許権は得られません。
・積極的な経営のすすめ
積極的な経営をするには、特許を取得するべきです。取引先や銀行の評価も違ってきます。最近では「知的資産」という用語まで存在し、知的財産の重要性が見直されております。
・特許出願しないと特許権は得られません。
特許取得のためには、まず特許出願という手続が必要です。特許出願は、発明の内容を文字と図面で詳細に記載しなければならず、素人の方では難しいです。これがネックとなって特許出願しない会社が多いのですが、不動産を購入した時に司法書士に登記申請を依頼するのと同じで、特許出願も弁護士や弁理士に依頼した方がいいのです。
・コンビニで買い物しているのと違います。
百均で売っているようなものから、航空機、テレビ、薬、建築など、技術はあらゆるものに含まれるため、弁護士や弁理士が全ての技術に対応できるはずがありません。その上、発明者が発明の内容を正確に伝えないといけないため、人と人とのコミュニケーションも重要で、個人的な相性の問題まであります。そこで、この人なら話しやすくて信頼できると思う弁護士や弁理士を見つけることが重要です。
・出願依頼の方法
発明の内容を、図や写真や(小さければ)実物で、ここがこうなるから、こういう効果が出ると詳しく説明すればいいのです。小学生に教えるぐらいの気持ちで書いた方がいいです。なぜなら、発明は手品みたいなもので、種明かしをしながら手品の手順を教えるのと同じです。特許になる発明はその時点で誰も考えつかなかったものなので、全てを知っているのは発明者だけなのです。その種明かしを省略して説明すると、なぜ?という疑問ばかり出て伝わらないのです。手書きでも大丈夫です。とにかくわかりやすく全てを説明することを心がけましょう。それが強い特許への第一歩です。
・特許出願から特許権発生までの流れ
特許出願→審査請求→審査→(拒絶理由通知)→特許査定→特許料納付→特許権発生 が一覧の流れです。
特許出願しても、審査請求をしなければ、特許庁では審査をしてくれません。これは出願した日から3年以内にしなければなりません。出願後3年以内に、もうこの技術は保護する必要がないと思うのなら、審査請求をしなければ余計な費用を削減できます。
審査は、特許庁の審査官という人らが行います。審査官は技術分野ごとに担当が分かれており、自らの専門知識も含めて、審査を行ってくれます。
審査の結果、この技術は特許すべきでないと判断されると拒絶理由が通知されます。その拒絶理由の内容を読み、もう無理と判断すれば、拒絶査定になります。しかし、内容を少し訂正したら(「補正」と言います。)、その拒絶理由が解消できる場合もあります。その時には意見書や補正書を提出します。そうすると、もう一度判断され、最終結果が通知されます。見事、特許査定になれば、特許料の支払い後に特許権が発生します。特許証という賞状のようなものまで送られてきます。